 |
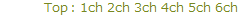 | |
|
Music Archive Review
| ||
|
| Bill Evans / Native and Fine(1995) | |
|---|---|
 |
1. Fling Ding 2. Native and Fine 3. Goodbye Liza Jane 4. Wondrous Love 5. Scotland Yard 6. Choking The Strings 7. Clarinet Polka 8. Omie Wise 9. Jump Jesse 10. Saalo's Joy 11. Chicken Pox 12. Midnight in Rosine |
| Bill Evans : Banjo Jason Carter : Fiddle Mike Compton : Mandolin David Grier : Guitar Missy Raines : Bass Stuart Duncan : Fiddle Suzanne Thomas : Vocal Ron Thomason : Vocal,Mandolin | |
| Label/No etc. | Rounder 0295 |
| お買い求め情報 | 輸入CDを置いているちょっと大きな店なら売っていると思います。「CDNOW JAPAN」http://www.cdnow.co.jp/で検索するとサウンドサンプルを聴くこともできます。もちろん、そのまま購入することも。 |
| 備 考 | ビル・エヴァンスのバンジョーはドライ・ブランチ・ファイアー・スクォッド(Dry Branch Fire Squad)『Live! at Last』(Rounder 0339)、スザンヌ・トーマス(Suzanne Thomas)『Dear Friends & Gentle Hearts』(Rounder 0423)でも聴くことができます。 |
「このCDに感動した!」という言い方を僕もよくしますが、「感動」と一口に言っても、その中身は非常に多岐にわたります。何かに打ちのめされてしまうような圧倒的な感動とか、いても立ってもいられないような気持ちの昂ぶりを引き起こされる感動とか、思わず胸がキュンとしてしまうような切ない気持ちにさせられる感動とか…まぁ、いろいろです。
ビル・エヴァンス(ジャズのビル・エヴァンスとは無関係です。念のため)の『Native and Fine』を初めて聴いた時に僕が覚えた感動は、言葉にすると「とても静かで安定した感じの感動」だったような気がします。半分くらい「感心」と言ってもいいような、「エライねぇ、この人は」というような、そういう感動です。そういう種類の感動は他のことによっても経験することはありますが、僕が聴いたブルーグラスのアルバムの中ではこの『Native and Fine』がNo.1です。
このアルバムには、土の匂いがプンプンするような山の音楽もあれば、そういう泥臭さとは無縁の街の音楽もあり、東欧・チェコはボヘミア地方の音楽「ポルカ」もあれば、「スコットランド」という地名を冠する曲や、ビル・モンローの生地(=ブルーグラスの聖地)ケンタッキー州ロジーンに思いを馳せた曲も収められていて、結果としてビル・エヴァンスの演奏スタイルもさまざまにならざるを得ず、そういう意味では一見(一聴?)すると非常に雑多な感じがしないでもありません。
しかし、ビル・エヴァンスの奏でるバンジョーの音を聴くと、この雑多な12曲が、ちゃんとつながっているのがわかります。「あぁ、これはブルーグラスだ」と感じてしまいます。まるで、ブルーグラスのツボのようなものがどこかにあって、ビル・エヴァンスはそれを熟知していて、それをいろいろなスタイルで小出しに(時にはモロ出しに)しているような、そんな印象を受けるのです。
こう書くと、まるでビル・エヴァンスが頭でっかちのヤなやつかのように思えるかもしれませんが、決して…いや、たぶん、そんなことはありません。このアルバムはたまたま落ち着いた感じに仕上がっていますが、上記ドライ・ブランチ・ファイアー・スクォッド(Dry Branch Fire Squad)『Live! at Last』(Rounder 0339)ではちょっとホットなビル・エヴァンスを聴くこともできます。まぁ、ちょっと、ですけど。
| Lonesome Standard Time / Mighty Lonesome (1993) | |
|---|---|
 |
1. The Bigger The Fool (The Harder The Fall) 2. I'm Lonesome And Blue 3. Sugar In The Gourd 4. Lonesome For You 5. I'm Lonesome Without You 6. Heaven's Green Fields 7. Kentucky Thunder 8. My Hands Are Tied 9. Bandit 10. Whistlestop Willie 11. The Sweetest Love 12. The Tracks We Leave |
| Larry Cordle : Guitar,Vocal Glen Duncan : Fiddle,Guitar,Vocal Billy Rose : Bass,Vocal Butch Baldassari : Mandolin Larry Perkins : Banjo | |
| Label/No etc. | SH-CD-3816 |
| お買い求め情報 | 輸入CDを置いているちょっと大きな店なら売っていると思います。 |
| 備 考 | ラリー・パーキンスのソロ・アルバム『A Touch Of The Past』もお薦めです。 |
ブルーグラス・ファンなら誰もがラリー・パーキンスのバンジョーを初めて聴いた時には、ある種の「衝撃」を受けたのではないでしょうか。
丸い身体に丸い顔、しかしその丸顔に柔和さは微塵も感じられず、頬ひげを蓄えた無愛想な表情はなんとも近寄りがたい雰囲気を醸し出しています。突き出たお腹の上にバンジョーを載せて、足はがに股、身体を小刻みに上下させながら黙々と演奏する姿はお世辞にもかっこいいとは言えません。
しかし、そんな外見とは裏腹に、彼のバンジョーにはあの「バンジョーの神様」アール・スクラッグスのトーンが宿っています。バンジョー弾きなら誰でも一度は「ああいう風に弾きたい」と思い焦がれ、「ああいう風には弾けない」と挫折する「スクラッグス・スタイル」を完璧に弾きこなす男、「神様」の右手を受け継いだ男(「神様」もまだ現役ですが…)、それがラリー・パーキンスなのです。
ラリー・パーキンスがロンサム・スタンダード・タイムに在籍したのは92年から93年までのわずか1年ほど、残したアルバムもこの1枚のみです。ロンサム・スタンダード・タイムにとってはこれが2枚目のアルバムで、1枚目『Lonesome Standard Time』(SH-CD-3802)も3枚目『Lonesome As It Gets』(SH-CD-3839)もそれはそれでよいアルバムなのですが、この『Mighty Lonesome』は、彼らの他のアルバムにはない「古めかしい」雰囲気が漂っていて、当時の僕にはそれがかえって新鮮に感じられ、意味もなく「これだっ!」と一人で熱くなっていたものです。
その「古めかしさ」の原因は、一つにはもちろんアール・スクラッグスを彷彿とさせるラリー・パーキンスのバンジョーにあるのですが、もう一つ、ビリー・ローズのタイトで躍動感あふれるベースがなかったらきっとこの「古めかしさ」はなかっただろうなぁ、という気がします。
3曲目「Sugar In The Gourd」を聴いてみて下さい。ラリー・パーキンスがいかにもスクラッグス風に明るいトーンで均等に8分音符を刻んでいると、途中からベースがつんのめるように前へ前へと引っ張って行き、全体がそれに巻き込まれて一つの「うねり」となって行きます。
こういうのって言わば「お約束」でもあり、「いかにも」という感じがしないでもないのですが、そういう古典的なドライブ感を求めてずっと演奏してきたせいか、知らず知らずのうちについついいい気持ちになってしまいます。ちょうど土俵入りをする横綱が四股を踏む時についつい「ヨイショー」と声をかけたくなってしまう…アレと同じですね。わかりにくくてすみません。
| Larry Sparks / A Face In The Crowd (1985) | |
|---|---|
 |
A1. Blue Ridge Mountain Mornings A2. Nobody's Business A3. Too Late To Worry A4. Lesco A5. Somehow Tonight A6. Guide Me Lord B1. A Face In The Crowd B2. Girl At The Crossroads Bar B3. Carter's Blues B4. Love Of The Mountain B5. Blue Ridge Ramble B6. Sitting In This Lonely Prison |
|
Larry Sparks :
Guitar,Mandolin,Voca
Tommy Boyd :
Dobro,Banjo,Vocal
David Bowling :
Bass
Glen Duncan :
Fiddle,Vocal Joe Isaacs : Banjo (B6) Dave Cox : Mandolin (B6) Bernice Sparks : Guitar (B6) | |
| Label/No etc. | Old Homestead 90161 |
| お買い求め情報 | CD化されていません。中古レコード屋で探して下さい。 |
| 備 考 | オリジナルは Lesco『Kinda Lonesome』。 |
ラリー・スパークスとデル・マッカリーとピーター・ローワンを、ブルーグラスのパイオニアたちに直接教えを受けた「第二世代」の三大ボーカリストと呼ぶのはいささか早計でしょうか?でも、とりあえず僕はそう思っています。他に「この人は?」という人がいたら、誰か教えて下さい。
僕は三人の中ではラリー・スパークスのボーカルに個人的にいちばん強く惹かれます。僕がラリー・スパークスを最初に聴いたのは、大学に入って間もない頃、先輩に録音してもらった『John Deere Tractor』(Rebel 1588)でした。その抑え気味の渋く渇いた声に思わずグッと来てしまいました。
デルもピーター・ローワンも、ビル・モンローの教え子だからでしょうか、比較的ハイ・テンションの張り詰めた雰囲気を売りにしていたような気がします。まぁ、それこそ「ハイ・ロンサム」なのかもしれないし、それはそれでとても刺激的で僕も大好きなのですが、ラリーは「ハイ・ロンサム」とは明らかに一線を画して、ソフトで、なおかつ芯もあり、クセもある、枯れた声を僕らに聴かせてくれます。
ラリー・スパークスから1枚と思っていろいろ考えてみたところ、前述の『John Deere Tractor』や『Silver Reflections』(Rebel 1654)も確かに素晴らしいのですが、学生時代のある時期に狂ったように繰り返し聴いたという個人的な思い入れで『A Face In The Crowd』にしてみました。今回、この原稿を書くために久しぶりにレコードに針を落としてみたのですが、B面1曲目「A Face In The Crowd」を聴くと今でもある種のバランス感覚を失いそうになります。大げさに聞こえるかもしれませんが、自分の周りにある空間がグニャっとねじ曲がったような感覚にとらわれて、自分もその歪みの中に飲み込まれてしまいそうになるのです。いや、ホントに、困ったものです。
4年前にラリーが来日した際に松本和茂先生が作られたラリーに関する詳細な資料によると、この『A Face In The Crowd』は1980年の作品となっています。僕の持っている『A Face In The Crowd』のレコードには1985年と書かれているのですが、グレン・ダンカンが参加していたのを考慮して録音時期を特定したのか、あるいはオリジナルの『Kinda Lonesome』には1980年と書いてあるのか、よくわかりません。が、曲目も1980年に録音された『John Deere Tractor』と結構ダブっていたりするので、おそらく1980年の録音なのでしょう。
この同時期に録音されたと思われる2枚を聴き比べてみると、『John Deere Tractor』が全体的に落ち着いた雰囲気に仕上がっているのに対して、『A Face In The Crowd』はより素朴で、雑駁で、よく言えば力強い、悪く言えば粗野な感じがします。この違いを生み出しているのはラリーのボーカルのせい…ではなく(どっちも枯れて渋いです)、明らかにグレン・ダンカンのフィドルのせいです。
ラリーのボーカルに「これでもか」と言わんばかりにからんで来るフィドルのバッキングは「耳障り」の一歩手前です。でも、これがあるからこそ、聴いているうちに空間が歪んできてしまうのです。後にラリー・コードルと組んでロンサム・スタンダード・タイムで一旗挙げるときに再確認することになるのですが、グレン・ダンカンって、ちょっとクドい感じのボーカルと組んだ時がいちばん魅力的ですね。
| John & Jamie Hartford / Hartford & Hartford (1991) | |
|---|---|
 |
1. Love Grown Cold 2. Run Little Rabbit 3. Killing Floor 4. When The Roses Bloom In Dixie Land 5. New Love 6. Sweet Sunny South 7. Painful Memories 8. Nobody's Darling But Mine 9. Put All Your Troubles Away 10.I Know You Don't Love Me No More 11.She's Still Gonna Break Your Heart |
| John Hartford : Banjo,Fiddle,Vocal Jamie Hartford : Mandolin,Vocal Roy M. Huskey Jr. : Bass Kenny Malone : Percussion Mark Howard : Guitar | |
| Label/No etc. | Flying Fish 70556 |
| お買い求め情報 | ちょっと大きなCDショップなら売っていると思います。 |
| 備 考 | |
大学3年目の時、前年留年してその年はほとんど授業もなく時間がたくさんあったので、せっせとアルバイトをしてお金を貯めて夏にアメリカへ行きました。フェスを2つ見て回ること以外に何の予定もないという、今考えるとずいぶん計画性もなくもったいない旅行でしたが、当時はそれだけあれば充分なような気がしていました。なんせビル・モンローもラルフ・スタンレーもデル・マッカリーもピーター・ローワンもトニー・トリシュカも…他にもたくさんの敬愛するミュージシャンを生で見ることができたのですから。
ジョン・ハートフォードを初めて見たのもその時でした。息子とベース弾きと、たった3人でいかにも楽しそうに、でも飄々と演奏するハートフォードを見ていると、なんとも言えず温かい気持になって胸がいっぱいになってしまいました。
このアルバムは、ちょうどその年に発売されたもので、その時のステージで演奏していた曲が多く収められています。特に4曲目「When The Roses Bloom In Dixie Land」のこのアレンジはそれからしばらくの間僕のお気に入りでした。「♪オーフェンーザロズィーズブルーミンディークシーラン」というところでベース音が徐々に下がっていくのがなんともいい感じです。
この曲はティム&モーリー・オブライアンの『Take Me Back』というアルバム(これも名盤ですよねぇ)にも入っていて、そっちもなかなか捨てがたいものがありますが、どちらかと言うとティム&モーリーがスマートに決めているのに対して、ハートフォードはのんびり、ゆったりと(決してテンポのことだけではなくて)演奏しているような気がします。都会に出稼ぎに出た若者が田舎に残してきた彼女に「金サたまったら丸太小屋でも建てて2人で住むべ」と言っている歌なので(たぶん)、まぁ、田舎者臭さを醸し出しているという点においてはハートフォード・ヴァージョンの方がそれっぽいかなぁ…と思わないでもありません。
ちなみに後年、オズボーン・ブラザーズもこの曲を取り上げていて、オズボーン・ファンの僕としてはそれはそれでまたなかなかオツなものなのですが、どうにも「若者らしさ」がないのがたまにきずです。ま、ブルーグラスの曲にそこまで求めるか、と言ってしまえばそれまでなのですが…。
| Gene Wooten / Don't Look Now (1994) | |
|---|---|
 |
1. Dobro Rhumba 2. Just Ain't 3. Coyote Song(AKA Montana Cowboy) 4. Foggy Mountain Rock 5. Don't Look Now 6. Southbound 7. Sunny Side Of Life 8. Wedding Bells 9. No Doubt About It 10. I'll Be All Smiles Tonight 11. I'm Gonna Love You One More Time 12. Flatt Lonesome 13. Preachin',Prayin',Singin' 14. Dobro Chimes |
| Gene Wooten : Dobro,Guitar,Vocal Mike Bub : Guitar David Crow : Fiddle Charlie Cushman : Banjo,Vocal Shelton Feazell : Vocal Tom Roady : Percussion Terry Smith : Bass Roland White : Mandolin | |
| Label/No etc. | Pinecastle 1024 |
| お買い求め情報 |
|
| 備 考 |
|
このアルバムはジーン・ウートンの初ソロアルバムです。この当時、すでに「若手」ではなくなっていた、感じのいいおじさん(本当にいい人です)が、自分の大好きな古い歌を本当に気持ちよく歌っている感じがひしひしと伝わって来ます。
このアルバムには際立った「新しさ」というような要素はそれほどないかもしれません。最初からそういうものを意図して作られていないのは、多くの曲が原曲にかなり忠実に、あまり手を加えられないスタイルで演奏されている様子からもよくわかります。たぶん、ジーンは自分の好きな古い曲を昔自分が聴いたようなスタイルで演奏するのが好きなんでしょう。そういう気持ちはブルーグラス・プレーヤーならとてもよくわかるのではないでしょうか(まぁ、ブルーグラスに限ったことではないと思いますが)。
もちろんブルーグラスの世界にも創造的で個性的で野心的で革新的な演奏というのはあって、それはそれでとっても刺激的で魅力的なのですが、どうも最近歳をとったせいか、音楽を聴いていても本を読んでいても映画を見ていても、「おれが、おれが」と情熱的に個性をアピールするようなものはちょっとギラギラし過ぎる感じがしてあまりうまくなじめないことが少なくありません。そして、ついつい思ってしまうのです。「個性的なことがそんなにいいことか?」と。
このアルバムを聴いていると、ジーンが過去の偉大なミュージシャンと「つながっている」ことを強く感じます。決して新しいスタイルを切り開いているわけではありませんが、ジーンが確実にフラット&スクラッグスの音楽を受け継いでおり、それが音楽として他のブルーグラス・プレーヤーあるいはリスナーの間でも引き継がれていることをしっかりと示しているような気がします。そして、音楽ってそういうものだよなぁ(というか、そういう部分もあるよなぁ)と、改めて思うわけです。
そういう眼で見てみると、「Don't Look Now」というタイトルはこのアルバムの持つ性格を実によく表していると言えなくもありません。きっと、ジーンの眼は古きよきブルーグラスをじっと見つめているはずで、偉大な過去とのつながりの中で現在をとらえようとしていたのではないでしょうか。ま、そんなの勝手な深読みに過ぎないとは思いますが…。
