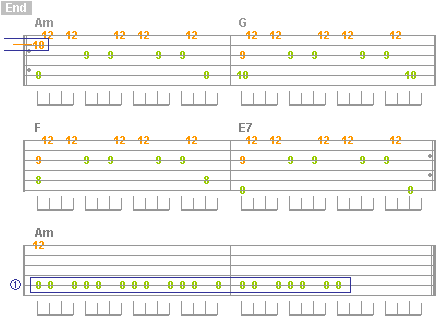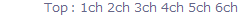
 |
Super Mario Bros. 太陽にほえろ! 主題歌 愛のテーマ 青春のテーマ サスペンス |
UFO サザエさん Suntory Old 列車内jingle |
妖怪人間ベム 夏のお嬢さん ふたりはプリキュア スナフキン |
ルパン三世 ゲゲゲの鬼太郎 泳げたいやき君 |
 |
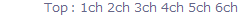 | |||||||
Guitar Archive
| ||||||||
|
|
イントロのイントロです。 エレキギターの主旋律(①)だけに耳を奪われがちですが、これを追いかけるピアノのフレーズ(②)を加えると、が然、雰囲気が出てきます。 |
|
なんて印象的で、そして危険なフレーズなのでしょう!オクターブ違いの2音をとり憑かれたように弾き続けるヤケクソフレーズ! 七曲署がいかに忙しいかが、このフレーズから想像できますね。 このオクターブ部③は、1弦12フレットを小指、3弦9フレットを中指で押弦し、ベース音は人差指で押さえます。 ベース音は、【5弦 開放】の後、【6弦 3f】→【6弦 1f】と行きたいところですが、オクターブ部を押さえながらということで、1オクターブ上に展開し、【5弦 10f】→【5弦 8f】を使用します。 緑色の数字は右手親指で、だいだい色は右手人差指又は中指で弾きます。 ちょっと弾いてみましょう。ゆっくり弾いても、意外とそれっぽい雰囲気になりますよ。 |
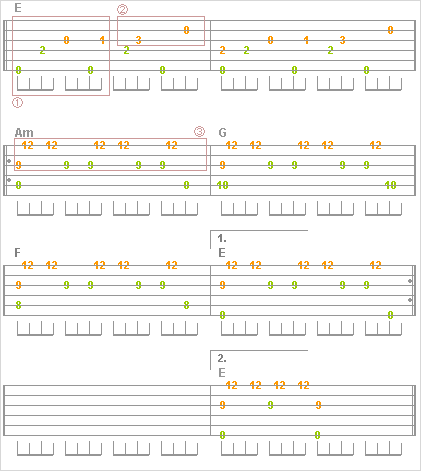
|
メロディだけを弾くなら、チャラチャー〜とよそ見をしてても弾けるくらい簡単なこの曲。 問題はそのゆったりしたメロディをよそに、猛然と16ビートを刻み続けるエレキ・ベースの存在です。 いくらメロディが簡単といっても、このハードなベースのリズムに重ねるとなると、これは結構ひと苦労ですよ。この曲のポイントはもう、そこに尽きましょう。 |
さてこの熱いエレキ・ベース、最初から熱いうえ、後半さらに燃え上がって手がつけられませんが、基本的には以下のようなリズムです。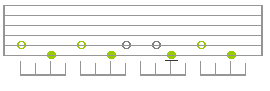 [凡例] ○ → ルート音 (Amであれば、A=ラ=5弦開放の音) ● → 5度下の音 (Amであれば、E=ミ=6弦開放の音) (下線で示した11/16拍目の音は、原曲ではルート音を弾いていますが、多少単調なのでここでは5度下でアレンジしています。) クチで言うと、こんな感じ。
|
|
このベース音で重要なのは、裏拍に当たる部分。上のリズム譜で示すなら灰色の ○ の部分、クチで言うパターンで示すと赤の デンデ の部分です。 これを的確なリズムで弾くことで、はじめて独特の「16ビート感」が出せるわけですが、これを親指のアップピッキングで弾こうとすると、 音量・リズムキープの両面で、かなり難があるため、ここは人差指を動員することとします。 人差指の方も、普段はもっぱら高音のメロディ部担当で4弦や5弦といった低い弦をはじくことが無いため結構違和感があるかと思いますが、ここは慣れることで克服しましょう。 なお、ベース音の基本的な動きは上に示した通りですが、ギターで出せる音域の関係上、5度下の音を1オクターブ上に展開させたり、 アクセントをつけるため裏拍の部分のルート音を1オクターブ上に展開させるなどしています。 |
以上のことから、右手各指の役割が決まりました。 各指が入れ替わり立ち替わり、複雑に出入りしますので、混乱をきたさないよう頑張ります。 |
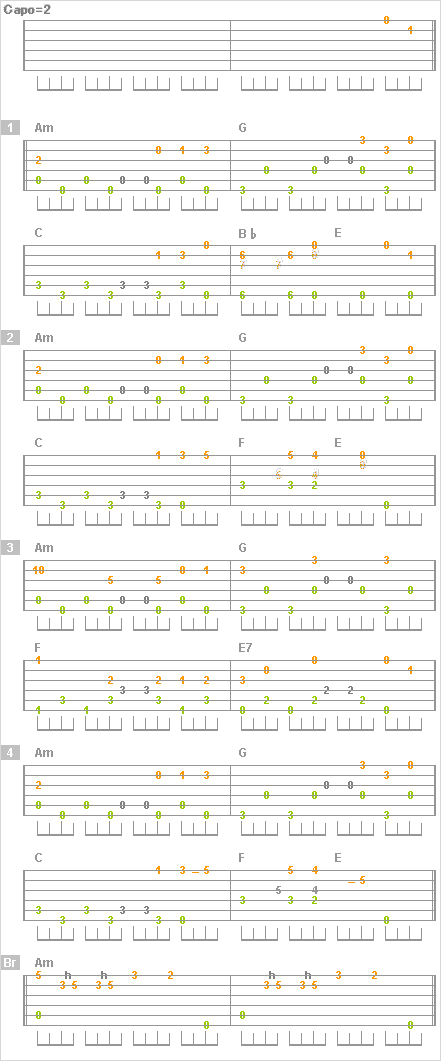
|
このブリッジ部!カッコいいですねー。 5&6弦とも開放ですから、①はドンデン!というブレーク感をうまく出しましょう。 リードギターの部分はいくら激しく弾いてもとがめる人はいないはずです。 |
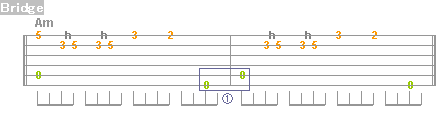
|
1回目の主旋律をそのまま繰り返してもOKですが、それでは飽きるという方用に、多少アレンジを施しています。 |
|
少々複雑ですが、ハンマリングを利用して弾きましょう。 ②は、フレーズの頭とベース音(5弦2フレット)が重なる形になります。 |
|
原曲を知る方ならよく分かると思いますが、なぜか突然挿入されるひずんだエレキ・ギターのフレーズ。 タイミング的には、メロディの「チャラッチャー」の「チャラ」の部分と重なっています。工夫して両方を弾くことも可能ですが、 あの「押しのけて入ってくる感じ」を再現するには、このフレーズだけを弾いた方が良いような気がします。 |
|
この「主旋律その2」は、原曲では前半4小節をオルガンが弾いており、後半再びサックスがハイ・トーンで突入してきます。
さしずめ第4コーナーで大外から突っ込んでくる感じ。 あの感じを出すため採用されたのが④のチョーキングです。 親指でベース音の5弦からメロディの2弦まで弾き下ろし、2弦の方はチョーキングへと入りつつ、親指の方は 何事もなかったように6弦、5弦〜とベース音を刻み続けます。親指の動きに気を取られると、チョーキングの方が 短くなっていまいますが、脳を別々に働かせ、ロング・トーンになるよう頑張りましょう。 最初の弾き下ろし時に、3・4弦は右手でミュートしますが、ノイズとして鳴ってしまってもそれはそれで独特のカオス感が 出るでしょう。 |
|
エンディングは例のオクターブのフレーズへと戻ります。 このオクターブ部分は左手人差指と小指を使うため、この⑤は中指で押さえ、そのまま10フレットへと上昇し、 同時に始まるオクターブのフレーズへとスムーズに入れるようにします。 |
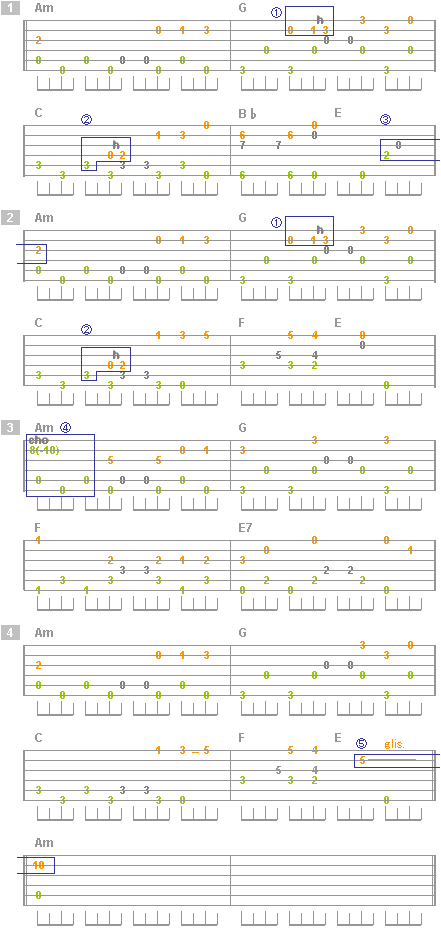
|
この「太陽にほえろ!」のテーマは、最後の最後まで聞き逃せません。それが①。 「ベベンベベベンベ〜」って、これだけ熱い演奏をした後に なぜこんな田舎くさいフレーズが・・・。 しかし、いつしかこの「ベベンベベベンベ」が、敵の断末魔のようにも、再び繰り返される惨劇のプロローグのようにも聞こえ、 この曲になくてはならない重要なパートとなっているのですね。 さあ、貴方も弾きましょう、この「ベベンベベベンベ」を! |